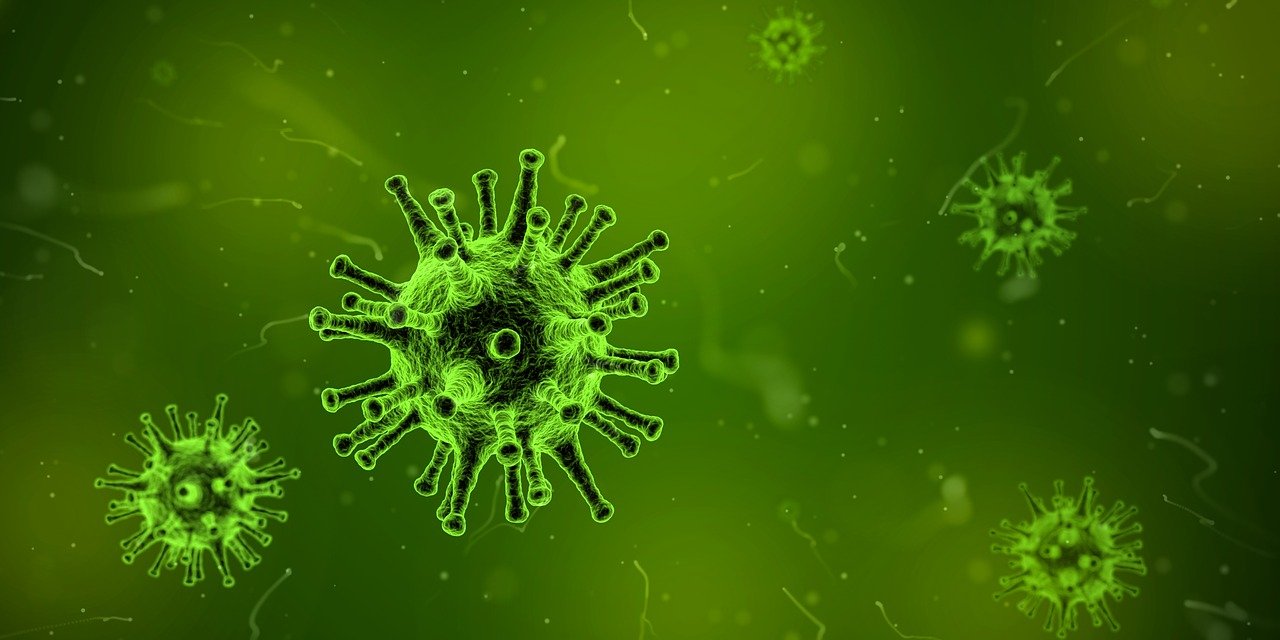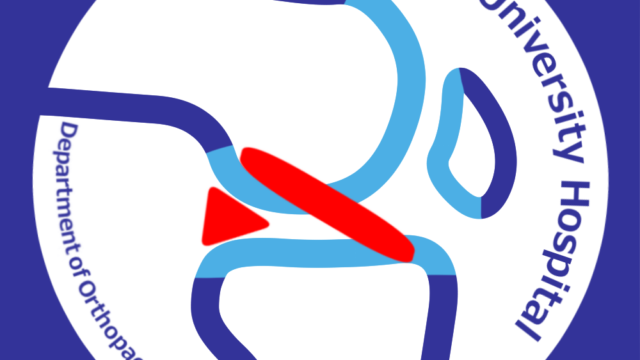この話は爆発的なパンデミックが起きた時のアメリカの女医さんの話です(英語の長文を日本語で要約をしています)。
原文を読みたい方はこちらをどうぞ。
https://www.newyorker.com/science/medical-dispatch/a-doctors-dark-year

現在、コロナウイルス第4波を迎えるにあたって、いろいろな意見をWeb上で確認することが出来ます。
貧しくも平和な日本は今後どのような方向に向かうのでしょうか?
医療崩壊なんてしないと考えている人は、どれだけ医療に精通しているのでしょうか?
医療従事者に対する考え方を少しでも変えるためのメッセージになれば幸いです。
この女医さんは、外傷外科医として研鑽を積んでいる中、ある日突然COVID-19の最重症患者を治療するI.C.U.に配属され、外科医ではなく主に内科医として働くことになります。
外科医でもあったためか、彼女は気道チームに抜擢されます。
この気道チームは、医師、看護師、呼吸療法士から構成され、主な任務は次の通りです。
- 酸素ボンベに接続されたマスクを患者の鼻と口に装着する。
- 誰かがベッドの頭を下げ、別の医師がカテーテルを静脈に導き(失敗すれば骨に穴を開ける)、
- 3人目が鎮静剤を投与する。
- さらに別の医師が患者の喉を覗き込んで声帯を盗み、プラスチックのチューブを挿入し、
- 他の医師が監視しながらC.P.R.(心肺蘇生)を行う準備をする。
医師であれば誰でも知っていることですがCOVID患者に対する気管挿管は、医療行為の中でも最もリスクの高いものと考えられています。
咳をされると、まるで死刑宣告を受けたような気分になりました。
毎日、これで終わりかもしれないと思っていました。
彼女は遺書を書き直し、両親にパスワードのありかや、人工呼吸器が必要になった場合の対処法を伝えました。自分が死んで、誰かが家に入らなければならなくなったときに、その人が感染するリスクを避けたかったみたいです。
そんな中、彼女は終わりのない気管挿管の重さを感じ始めます。
挿管チームの一員になるということは、患者や家族から死への切符と見られる人間になることを意味している。
人々を助けるために医学を志したのに、今では彼らが恐れる人間になってしまった。
そんな過酷な状況はさらに悪化します。
I.C.U.には手の施しようのないコロナウイルス患者があふれ、彼女をはじめとするスタッフは、呼吸が停止した患者の挿管作業に追われ、それでも救急外来には日に日に多くの患者が押し寄せ、ゼーゼー、ヒューヒューという悲しくもつらい音に満たされていきます。
私たちは、人々を回復させることに長けているはずでした。
私たちは人々を回復させるのが得意なはずなのに、代わりに死体を扱うのが得意になってしまったのです。
多くの不都合な死は、彼女を徐々にP.T.S.D.に侵していきます。
彼女には子供が2人いました。彼女は子供たちの面倒を両親にお願いすることになります。
両親のいるダラスまで飛行機で向かいます。ダラスのターミナルは旅行者の数も少なくなっていたようです。
父親が近づいてきて彼女を抱きしめようとすると、
お父さん、離れていてね
と彼女は言います。
二人の子供を空港内の家族用トイレに連れて行き、服を脱がせて体を拭く。
子供たちにはパジャマを着せ、旅行用の服は別の袋に入れて持ち帰ります。
ターミナルの外で遠くから手を振って別れを告げ、自分のゲートに向かって歩き出します。
コロナウイルスで死亡した医師がいることは勿論知っています。
子供たちに会えるかどうかも分からないまま、ボストン行きの飛行機に乗り込みます。
2020年6月、ボストンでは、感染者のペースが落ち始めました。北東部では感染者が減り、マサチューセッツ工科大学の臨時I.C.U.の一部も解体され始めました。
そんな中、彼女は依然としてCOVID患者を診ていて、悪夢が続いていました。
・・・彼女は患者の部屋に向かって走ったが患者を治療することはできなかった。アラームや人工呼吸器の音の中で息を切らしている患者を窓越しに見つめた。そこで、子供たちと永遠に引き離される自分の姿を見る・・・。
彼女は病院を移ることになり、ようやく、彼女の専門の外傷外科医をすることが出来るようになります。
転勤先ではコロナウイルスの感染率は低く、病院はほぼ正常に運営されていて、彼女は手術室に戻ります。
1日のうちに30人の患者を診て、5~10人を手術する。
患者のほとんどは、バイク事故や銃創などの深刻な外傷を負っており、緊急手術を受けなければ生きていけない状態。つまり、以前の医師生活に戻ることが出来たのです。
自分の医師としての役割を再確認できる日々がしばらく続きます。
しかし、急性外傷で病院に運ばれた人が、コロナウイルスに感染していることが増えてきます。
数週間後には、コロナウイルスの感染者が爆発的に増え、駐車場にテントを張って患者管理を始めます。
こんなことが繰り返されるはずがない
そう思いながらI.C.U.のドアを開けると、心臓がバクバクしてくる。
手のひらがベトベトになり、目がかすみ、胸が熱くなる。
胸が締め付けられるような不安感に襲われることも。
時には、動けない、考えられないといった麻痺状態に陥ることもあった。
そんな精神状態でも外傷外科医として役割を果たす傍ら、COVID患者を見なければいけない。
2020年10月、彼女が手術した患者(COVIDとは関係ない患者)が、ひどい合併症を起こして亡くなった。
彼女は、自分の手技に間違いがなかったかどうか思いを巡らせながら、車を走らせた。
家に近づいたとき、彼女はこう考えます。
もう、自分はいなくなったほうがいい
これを最後に、彼女はメンタルヘルスに入院します。もちろん、仕事は離れています。
P.T.S.D.が初めて病気として認識されたのは、ベトナム戦争の後でした。
P.T.S.D.には、不安、悪夢、フラッシュバック、気分の変化、解離性エピソードなど、さまざまな症状があり、その強さや特徴もさまざまです。
戦闘、交通事故、性的暴行、I.C.U.の滞在など、様々な種類のトラウマに引き続いて起こります。
症状は、きっかけとなる出来事の直後に始まることが多いですが、数年後に始まることもあり、数ヶ月、数年、あるいは一生続くこともあります。
今回のパンデミックでは、アメリカの医療従事者の4分の1がP.T.S.D.の症状を訴えています。
臨床医はパンデミックの間、並外れた精神的苦痛を受けました。
多くの臨床医が、不安、鬱、自殺願望、心的外傷後ストレス障害の症状を報告しています。
しかしながら、パンデミック以前から、アメリカの医師が自殺で亡くなる確率は一般の人々よりもはるかに高く、研修医の3分の1近くが鬱病を患い、医学生の10%以上が自殺願望を持っているといいます。
現在では、ワクチンのおかげで、パンデミックによる医療上の危機感は薄れつつあります。
しかし、患者や医師のメンタルヘルスへの影響はまだ残っています。
物資の不足、大切な人を危険にさらすことへの不安、患者の治療がうまくいかないことへの恐怖や罪悪感、死や病気への恐怖など、さまざまな原因が考えられます。
医師は、過酷な職業であるがゆえに波風が立たないと思われていますが、今回の未知のウイルスが発生していなくても、精神的・感情的に疲弊していることを理解してほしいのです。